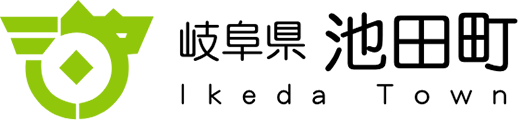あしあと
- 2025年6月10日
- ID:401
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
納めなければならない人(納税義務者)
国民健康保険税は、地方税法および町条例の規定により被保険者の属する世帯の世帯主に課せられます。
そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内で国民健康保険に加入している方がいれば、納税通知書等は世帯主に送付されます。
令和7年度の納期
| 納期 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 令和 7年 6月30日(月) |
| 第2期 | 令和 7年 7月31日(木) |
| 第3期 | 令和 7年 9月 1日(月) |
| 第4期 | 令和 7年 9月30日(火) |
| 第5期 | 令和 7年10月31日(金) |
| 第6期 | 令和 7年12月 1日(月) |
| 第7期 | 令和 7年12月 25日(木) |
| 第8期 | 令和 8年 2月 2日(月) |
| 第9期 | 令和 8年 3月 2日(月) |
| 第10期 | 令和 8年 3月31日(火) |
※納期限は通常月末ですが、休日(土、日、祝日)に重なる場合は、翌月初日の平日に繰り下げられます。
※令和7年度から仮算定廃止に伴い、納期を変更しました。詳しくはコチラ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
保険税の算定
国民健康保険税は、4月から翌年3月までの12か月分を第1期から第10期(納期限は6月から翌年3月)の最大10回に分けて納めていただきます。6月に本算定の納税通知書(第1期から第10期)を送付します。
6月の本算定以後に国民健康保険資格の変更(社会保険加入により国保離脱など)や、税額の変更(確定申告書の提出による所得の変更など)があった場合は、お手続きいただいた翌月に税額の変更(決定)通知書を送付します。
本算定について
本算定とは、前年中の確定所得金額と当該年度の国民健康保険税率をもとに年税額を確定(決定)するものです。
毎年6月中旬に発送される納税通知書で、第1期から第10期の10回の納期で分けて納めていただきます。
※令和7年度から仮算定が廃止されました。詳しくはコチラ(別ウインドウで開く)をご覧ください
税率などについて
| 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
|---|---|---|---|
| 所得割額(税率) | 5.50% | 1.95% | 2.30% |
| 均等割額(1人当たり) | 20,000円 | 7,000円 | 10,000円 |
| 平等割額(1世帯当たり) | 20,000円 | 8,000円 | 5,000円 |
| 限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
※税制改正に伴い、令和7年度から医療分の限度額が65万円から66万円に、後期高齢者支援金分の限度額が24万円から26万円に変更になりました。
国民健康保険税の後期高齢者支援金について
平成20年4月よりスタートした「後期高齢者医療制度」の一部を支援するものとして新設され、医療給付費分と同様に0歳から74歳の加入者全員がいままでの医療給付費分に後期高齢者支援金分(以下後期支援金分)をあわせた合計額を国民健康保険税として納付していただくことになります。
国民健康保険税の介護納付金について
平成12年4月から介護保険制度がスタートしておりますが、40歳から64歳の人は、医療給付費分と後期支援金分と介護納付金分をあわせた合計額を、国民健康保険の保険税として納付していただくことになります。
介護納付金の納付額は、国民健康保険の医療給付費分と同様に、年度単位(4月から翌年の3月)で計算されます。
前年中の所得が確定した本算定(7月)以降に、年税額から仮算定額を差し引いた分を、第3期から第10期の8回にわけて納付していただくことになります。
計算式
年税額は基本的に以下の計算式から算出されます。
- 所得割額(前年中の基準総所得金額×税率)
医療給付費分… 0歳から74歳の加入者全員の(基準総所得合計額-43万円)×5.50%=A
後期支援金分… 0歳から74歳の加入者全員の(基準総所得合計額-43万円)×1.95%=B
介護納付金分…40歳から64歳の加入者全員の(基準総所得合計額-43万円)×2.30%=C
※基準総所得額は所得の種類によって異なります。
・給与所得者 給与所得控除後の額
・給与所得者以外 総収入-必要経費-純損失
・公的年金収入者 年金収入金額-公的年金などの控除額 - 均等割額(被保険者1人当たり)
医療給付費分… 0歳から74歳の加入者数×20,000円=A
後期支援金分… 0歳から74歳の加入者数× 7,000円=B
介護納付金分…40歳から64歳の加入者数×10,000円=C - 平等割額(1世帯当たり)
医療給付費分… 0歳から74歳の加入者がいる世帯1世帯あたり20,000円=A
後期支援金分… 0歳から74歳の加入者がいる世帯1世帯あたり 8,000円=B
介護納付金分…40歳から64歳の加入者がいる世帯1世帯あたり 5,000円=C
※1.から3.の医療給付費分Aの合計額+後期高齢者支援金分Bの合計額+介護納付金分Cの合計額=年税額
(但し、それぞれの合計額が限度額を超える場合は限度額となります。)
低所得世帯に対する軽減措置(均等割額・平等割額)
世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者の前年所得の合計額が一定額以下の世帯に対し、均等割額および平等割額が以下の割合で軽減されます。
軽減割合 | 判定基準 |
|---|---|
| 7割 | 所得額が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 |
| 5割 | 所得額が43万円+{30万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 |
| 2割 | 所得額が43万円+{56万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 |
特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一世帯に属する方。
給与所得者等・・・給与収入が55万円以上の方、65歳未満で年金収入が60万円以上の方、65歳以上で年金収入が110万円以上の方、のいずれかに該当する方。
※軽減判定の所得は、税額を計算する際の所得と次の点で異なります。
- 専従者給与は、支払者の所得として計算します。
- 譲渡所得は、特別控除前の所得で計算します。
- 65歳以上の方の年金所得は、15万円までを控除した所得で計算します。
※軽減を受けるための申請は不要ですが、前年中の所得の申告がない世帯は軽減が受けられませんので必ず申告してください。
※税制改正に伴い、令和7年度から5割軽減と2割軽減の判定基準が変更になりました。
| 軽減割合 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 5割軽減 | 所得額が43万円+{29万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 | 所得額が43万円+{30万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 |
| 2割軽減 | 所得額が43万円+{54万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 | 所得額が43万円+{56万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 |
未就学児にかかる国民健康保険税の減額措置(均等割額)
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額について2分の1が減額されます。
減額の対象者
国民健康保険加入者のうち、未就学児(小学校入学前の児童)が属する世帯の国民健康保険税納税義務者
減額の内容
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。
低所得世帯に対する軽減措置(7割・5割・2割)が適用されている場合は、その割合を軽減した上で、さらに均等割額の2分の1を減額します。
| 法定軽減割合 | 均等割額 (減額前) | 適用減額 | 課税額 (減額後) |
|---|---|---|---|
| 7割軽減世帯 | 8,100円 | △ 4,050円 | 4,050円 |
| 5割軽減世帯 | 13,500円 | △ 6,750円 | 6,750円 |
| 2割軽減世帯 | 21,600円 | △10,800円 | 10,800円 |
| 軽減なし世帯 | 27,000円 | △13,500円 | 13,500円 |
表中の均等割額は医療給付分(20,000円)と後期高齢者支援金分(7,000円)の合計額です。
※この減額措置を受けるための申請は不要です。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者)がいる世帯についての軽減措置
国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移られた方を、特定同一世帯所属者といいます。
特定同一世帯所属者となることで、国民健康保険の加入者が1人だけになる世帯については、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険税のうち平等割額の2分の1が軽減されます。(特定世帯といいます。)
また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます。(特定継続世帯といいます。)
※軽減を受けるための特別な手続きは必要ありません。
※後期高齢者医療制度に移行した後に、世帯主変更などがあった場合は、軽減が適用されなくなります。
※医療給付費分・後期支援金分の平等割が対象であり、介護納付金分の平等割は軽減されません。
社会保険の被扶養者であった人への減免
社会保険の被扶養者であった人については、今まで保険料がかかりませんでしたが社会保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その人の被扶養者が国民健康保険に加入すると、保険税(料)がかかることになります。このことによる急激な負担を軽くするために、被扶養者であった65歳以上の人について、申請により以下のような減免を受け付けます。
- 被扶養者であった人(65歳以上)の保険料の所得割額を免除
- 被扶養者であった人(65歳以上)の均等割額を半額
- 被扶養者であった人(65歳以上)のみの世帯の場合は、平等割額を半額
※均等割額、平等割額の減免について、低所得世帯に対する軽減措置の適用となる世帯においては、軽減割合の高い方を適用します。
非自発的失業者の保険税の軽減
倒産、解雇、雇い止め等、会社の都合等で離職を余儀なくされた65歳未満の失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険料(税)の負担軽減策を講じます。【平成22年4月施行】
軽減対象者
軽減の対象者は次の2つにあてはまる方です。
- 離職時の年齢が65歳未満の方
- 離職の翌日から翌年度までに、雇用保険の【特定受給資格者】、【特定理由離職者】のいずれかの失業給付を受給されている方
【特定受給資格者】…例:倒産、解雇などによる離職
【特定理由離職者】…例:雇い止めなどによる離職
軽減措置の概要
失業時からその翌年度末までの国民健康保険税の算定の際、離職者にかかる前年の給与所得を「100分の30」として算出します。
高額療養費などの所得区分の判定についても、離職者にかかる前年の給与所得を「100分の30」として対応します。
申請の際に必要なもの
- 資格確認書、または資格情報のお知らせ
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークにて発行されます。)
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!